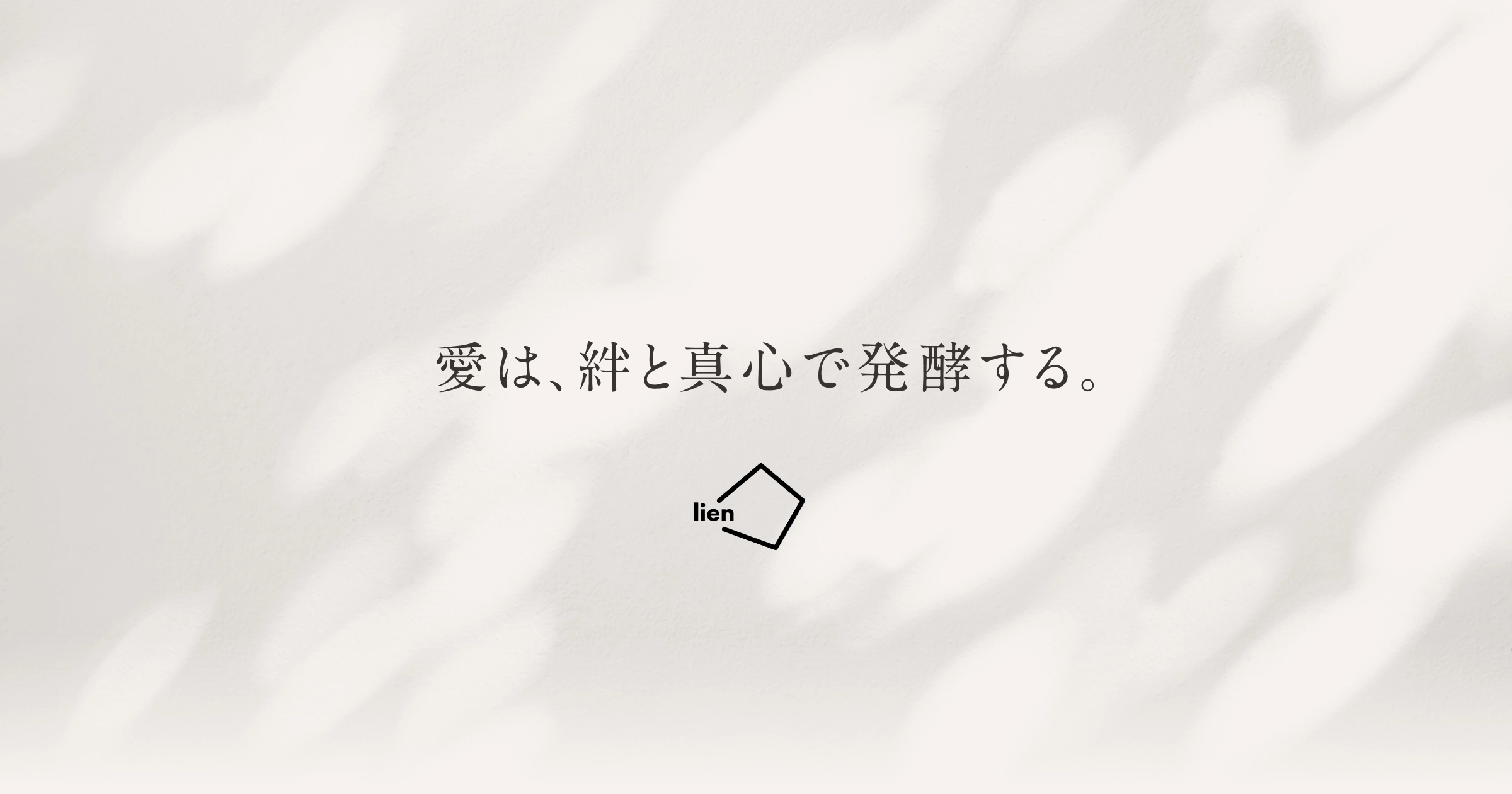【燕vol.4】ツバメの巣はどこで採れる? ──主要産地と中国の“採れないのに消費国”の真実

ツバメの巣はどこで採れる?──主要産地と中国の“採れないのに消費国”の真実
こんにちは、時 昴です。
今回は「ツバメの巣研究室」第5章として、ツバメの巣の採取地と、最大の消費国・中国との関係性をお届けします。
■ 世界でも限られた「採取できる国」
燕の巣、つまり“食べられる巣”をつくるのは、アナツバメというツバメの一種。
その巣は「燕窩(えんか)」と呼ばれ、主に以下の5カ国で採取されています:
- インドネシア
- マレーシア
- タイ
- ベトナム
- カンボジア
いずれも、温暖で湿度が高く、自然音や天敵の少ない“ツバメにとって理想的な環境”が整っている国々です。
■ 採り方にも2種類ある
- 天然洞窟型:自然の岩場や洞窟に巣をつくる。希少価値が高く、価格も高い
- 人工バードハウス型:人が管理する建物内に巣をつくらせる。供給が安定しやすい
私たちが扱っているのも、環境保全と品質管理を徹底した“管理型バードハウス”です。
■ 中国では……実は、採れない!?
最大の消費国である中国。
しかし、驚くべきことに──中国国内では、アナツバメはほぼ絶滅状態です。
かつては広東省や海南省などに生息していた記録もありますが、
都市化・環境破壊・気候変動などの影響で、今では野生個体を見ることはほとんどできません。
■ なのに、なぜ「最大の消費国」なのか?
それは、文化と市場の力です。
- 燕の巣は皇帝に献上された歴史ある宮廷料理
- 楊貴妃や西太后も愛用した“美と長寿の象徴”
こうした文化的背景が、燕の巣に対する絶対的なブランド価値を支えています。
■ 爆発的に増えた「輸入量」
中国では2015年、輸入量はおよそ20トンでしたが、
わずか2年後には80トン超を記録。
今や、燕の巣市場は1兆円規模にまで成長しています。
主な輸入先はインドネシア・マレーシアで、日本企業の参入も進んでいます。
■ いま問われるのは、“産地”より“哲学”
これからの時代、選ばれるのはただ「どこで採れたか?」ではありません。
・どう育てられたのか?
・どんな哲学で届けられているのか?
この“背景”にこそ、本質的な価値があると、私たちは考えています。
📌 まとめ
ツバメの巣は、アジアの自然と文化が育んだ天然資源。
そして今、それは“国際的な健康資源”として世界で取引されています。
最大の消費国・中国が“採れない国”であるという事実は、
市場の信頼や文化的価値がいかに重要かを物語っています。
📩 次回予告|
次回は、「日本のツバメ」と「アナツバメ」の違いについて。
驚くほど異なるその生態を、わかりやすくお届けします!